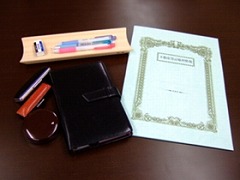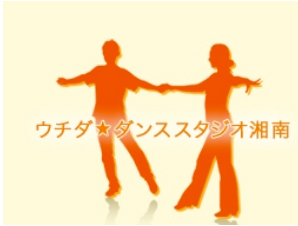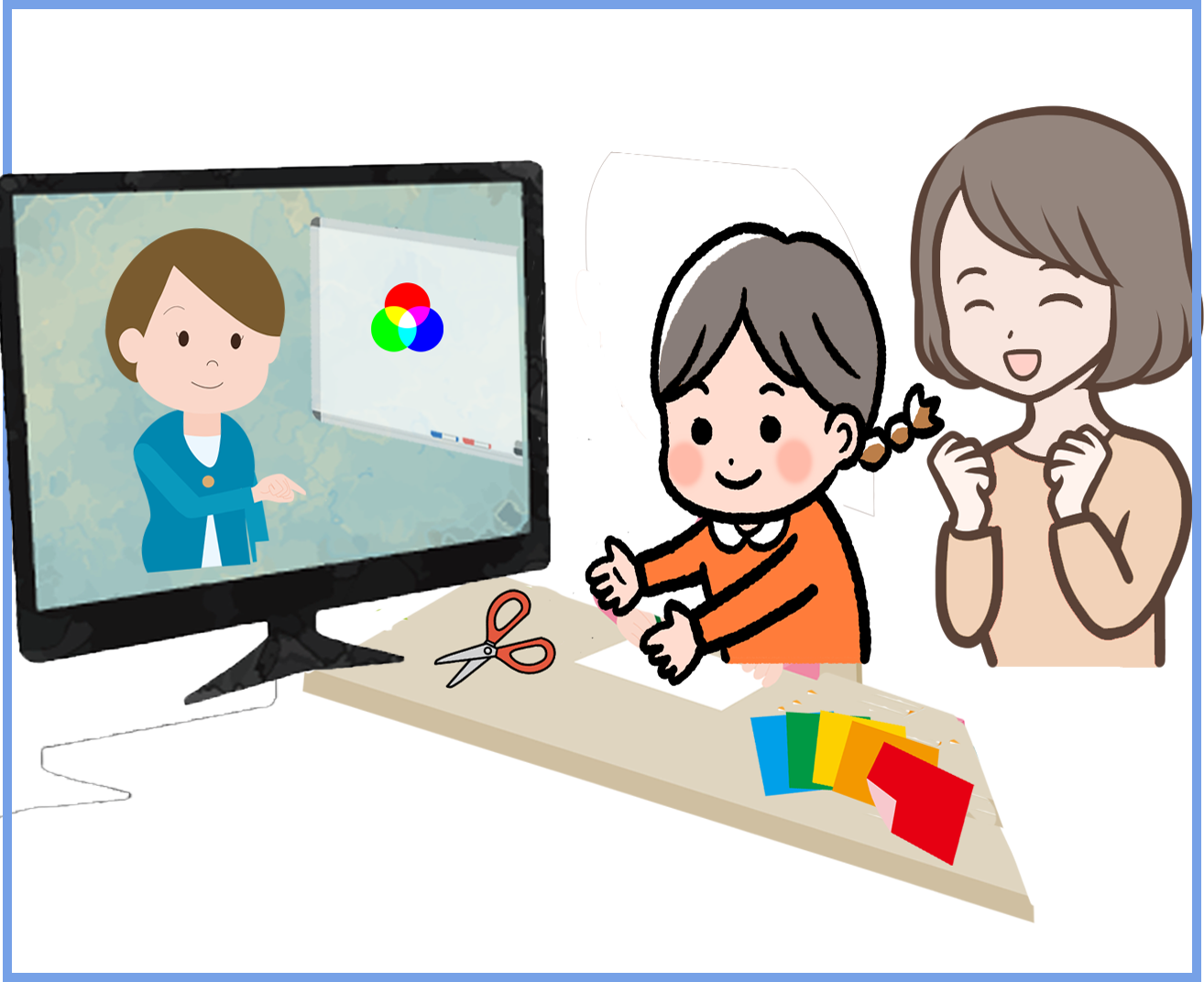アカメガシワは,落葉高木で高さは5~10㍍になります。江の島では比較的日当たりのよい場所で見ることができます
アカメガシワは,落葉高木で高さは5~10㍍になります。江の島では比較的日当たりのよい場所で見ることができます 江の島の植物・落葉高木≪アカメガシワ(赤芽槲)≫
2015年5月13日 (写真&文:坪倉 兌雄)
 江の島の東側斜面に咲くアカメガシワの花アカメガシワ(赤芽槲) 江の島の東側斜面に咲くアカメガシワの花アカメガシワ(赤芽槲) Mallotus japonicus トウダイグサ科アカメガシワ属 アカメガシワは秋田県以西から沖縄に分布し、山野に生える落葉高木で高さは5~10㍍になります。江の島では比較的日当たりのよい場所で見ることができます。雌雄異株。樹皮は灰褐色で網目状の裂け目ができ、冬芽、若木、葉などに星状毛が密生します。葉は互生し、長さ10~20㌢の倒卵状菱形で、ときに浅く3裂、基部近くに1対の腺点があります。葉の先端はとがり、赤くて長い葉柄をもちます。5~6月、その年に伸びた枝先に長さ7~20㌢の円錐花序をだし、花弁のない小さな花を多数つけます。雄花は淡黄色で萼は3~4裂し、雄しべが多数あり、花糸の長さは約3㍉。雌花の萼は2~3裂し、子房には刺状の突起があり、紅色の星状毛に覆われて、その先に3個の花柱がそりかえります。 |
|
 江の島の東側斜面に咲くアカメガシワの花 江の島の東側斜面に咲くアカメガシワの花 |
 淡黄色の花を多数つける雄花 淡黄色の花を多数つける雄花 |
 雄花の花糸がよく目立つ 雄花の花糸がよく目立つ |
 やわらかい刺のついた実(蒴果) やわらかい刺のついた実(蒴果) |
 実がはぜて黒い種子が飛びでる 実がはぜて黒い種子が飛びでる |
|
花柱には無数の突起が密生し、紅色から成熟すると青色になります。果実は蒴果で直径は約8㍉、やわらかい毛が密生し、9~10月に褐色に熟すと3~4裂して、黒い種子を3~4個だします。アカメガシワはヤシャブシやカラスサンショウなどと同じく、二次遷移の初期にでてくる先駆木本種(パイオニア樹種)で、潮風にも強く、江の島の日当たりのよい海辺でも見ることができます。アカメガシワの樹皮や葉には薬効成分があり、古くから民間薬として胃腸薬や胆石、はれものなどに用いられてきました。名前の由来は新芽が紅いことから「赤芽」、葉に食べ物を包んだりのせたりしたことから「かしは(炊し葉)」で、アカメガシワ(赤芽槲)と呼ばれ、サイモリバ(采盛葉)やゴザイバ(五菜葉)などの別名もあります。 |