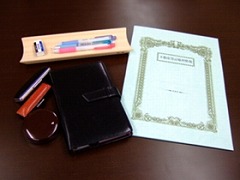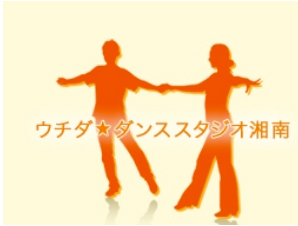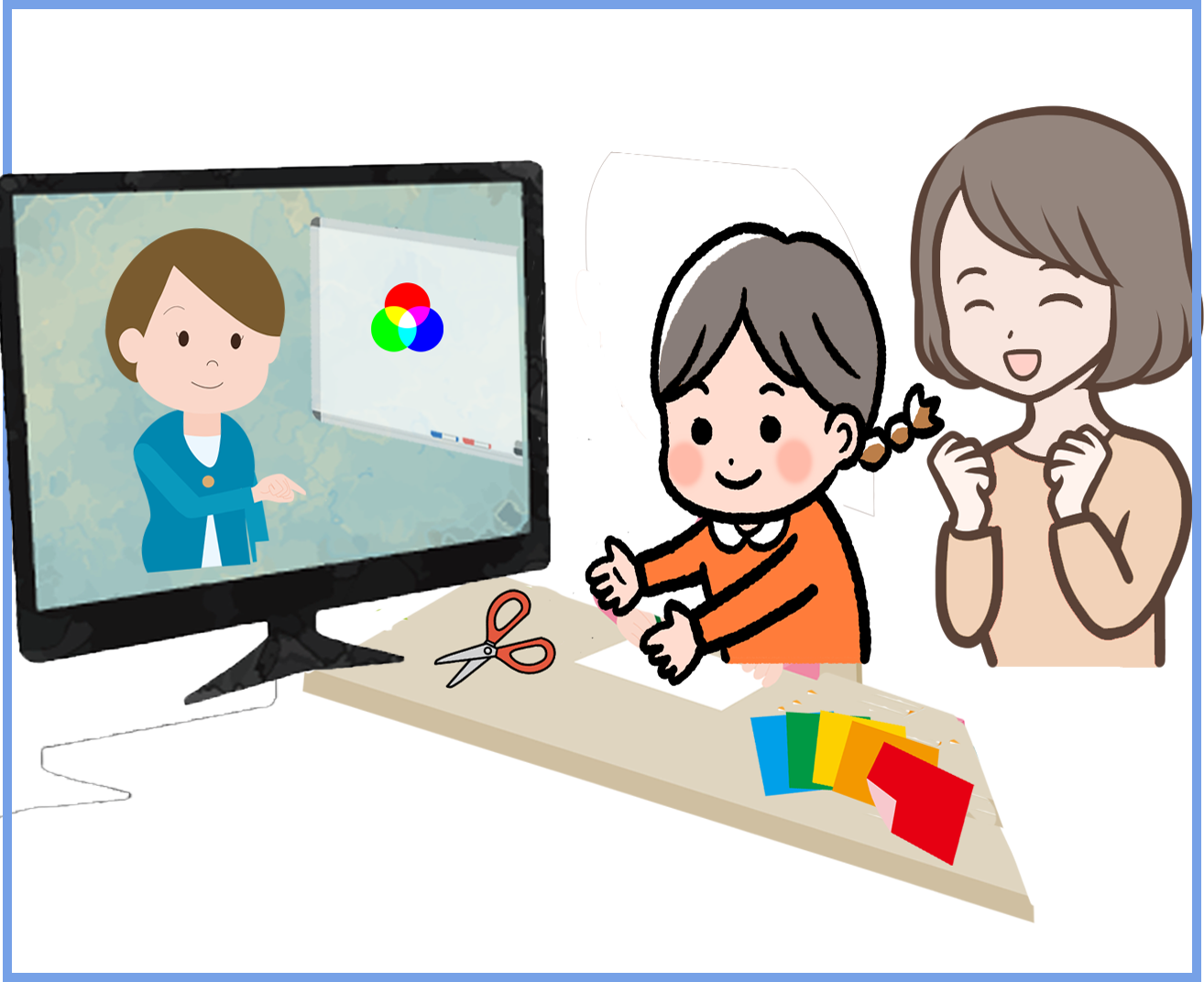オオバイボタは本州~九州に分布。江の島では広場や海辺の山側、龍野ヶ岡自然の森などで普通に見ることができます。
オオバイボタは本州~九州に分布。江の島では広場や海辺の山側、龍野ヶ岡自然の森などで普通に見ることができます。 江の島の植物・半落葉低木 ≪オオバイボタ(大葉水蝋)≫
2015年6月10日 (写真&文:坪倉 兌雄)
 龍野ヶ岡自然の森に咲くオオバイボタ江の島の植物・半落葉低木 ≪オオバイボタ(大葉水蝋)≫ Ligustrum ovalifolium 龍野ヶ岡自然の森に咲くオオバイボタ江の島の植物・半落葉低木 ≪オオバイボタ(大葉水蝋)≫ Ligustrum ovalifolium モクセイ科イボタノキ属 オオバイボタは本州~九州に分布する半落葉低木で、暖地の海岸近くに生え、刈り込みに強く庭木や公園樹などに用いられています。江の島では広場や海辺の山側、龍野ヶ岡自然の森などで普通に見ることができます。高さは2~5㍍になり、枝は灰褐色。葉は対生して長さは4~10㌢、楕円形~倒卵形で変化に富み、質はやや厚くて無毛、光沢があり先端は尖り、葉脈が鮮明で、かざすと透けて見えます。6~7月、本年枝の先に長さ5~10㌢の円錐花序をだし、白い花を多数つけ、花冠の長さは約8㍉の筒状漏斗形で先が4裂します。雌しべは短く、雄しべは2個で葯は花冠から突き出ます。果実は直径7~9㍉の球形で10~11月に黒紫色に熟します。強い潮風を受けるところでは、晩秋に落葉がはじまり、1月中旬にはほとんど葉はなくなりますが、幼木や潮風の影響をあまり受けない場所の成木は葉を残します。 |
|
 本年枝の先に円錐花序を出す 本年枝の先に円錐花序を出す |
 花は筒状漏斗形で先は4裂し葯が突き出る 花は筒状漏斗形で先は4裂し葯が突き出る |
 葉は対生して葉脈は透ける 葉は対生して葉脈は透ける |
 果実は球形で黒紫色に熟す 果実は球形で黒紫色に熟す |
 イボタノキの葉先は丸く花は総状花序 イボタノキの葉先は丸く花は総状花序 |
| 江ノ島には仲間のイボタノキ(Ligustrum obtusifolium)も自生しており、枝は灰白色、葉の長さが2~6㌢と、やや小形で先端は丸く、花は2~4㌢の総状花序を出すことなどから、オオバイボタと見分けることができます。イボタノキの枝にはイボタロウムシ(イボタロウカイガラムシ)が寄生し、雌の成虫は春に球形の小さな貝殻をつけてそこに卵を産み、卵は6月頃に孵化します。雄の幼虫は7月頃、枝に白色の蝋物質(イボタ蝋)を分泌して、その中で蛹になり、9月頃に羽化して飛び出します。残されたこのイボタ蝋は脂肪酸のセロチン酸などを含み、古くから「いぼ取り」に使用され、生薬では「虫白蝋(ちゅうはくろう)」と呼ばれています。またイボタ蝋は家具の艶出しや敷居の滑りなどにも使用されてきました。イボタノキの名前は、「疣取る木」が「イボタノキ」に転訛したもので、ここで取り上げた葉が大きいものを「オオバイボタ」と呼びます。 | ||