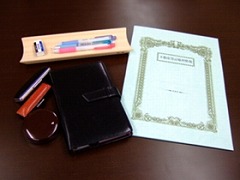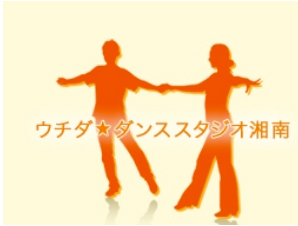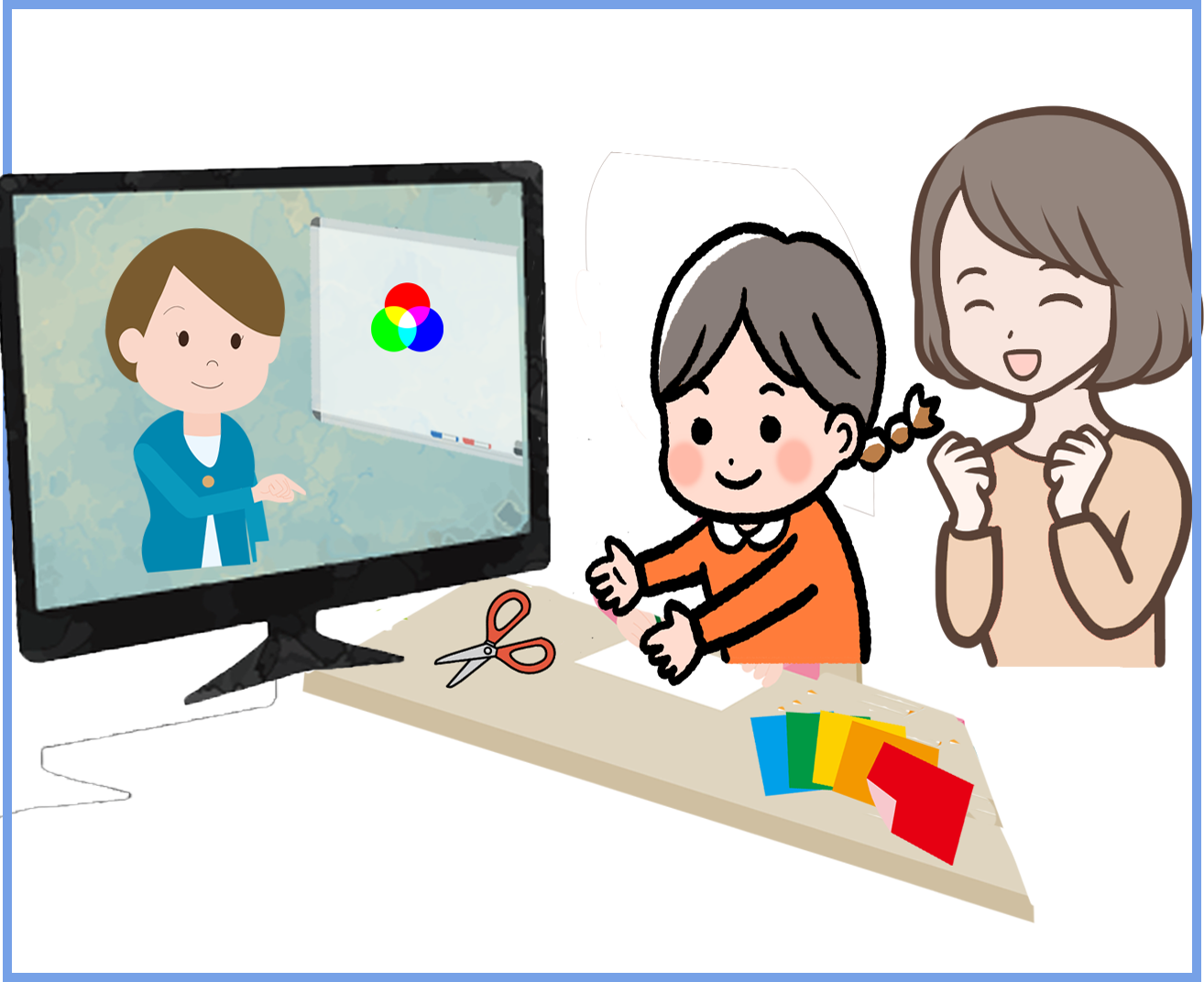江の島の植物・常緑小高木≪ツカミヒイラギ≫
2017年4月12日 (写真&文:坪倉 兌雄)
|
ツカミヒイラギOsmanthus heterophyllus var undulatifolius モクセイ科モクセイ属
|
|
 11月下旬、葉腋に白い花を束生する 11月下旬、葉腋に白い花を束生する 葯が目立ち、中央の緑色の部分は子房 葯が目立ち、中央の緑色の部分は子房 |
|
 ツカミヒイラギ ツカミヒイラギ 葉の裏側 葉の裏側 ヒイラギには鋭い鋸歯がある ヒイラギには鋭い鋸歯がある |
|
| 中央には雌しべがあり、花柱下部の緑色の部分は子房で頂上は柱頭です(写真参照)。子房は大きく発達することなく、翌年の1月中旬頃までにはほとんどが脱落します。ツカミヒイラギの名は、ヒイラギ(Osmanthus heterophyllus)の変種で、ふちに刺状の鋭い鋸歯がなく、つかんでも痛くないことから「つかみ柊」になったとされています。ヒイラギの葉は革質で光沢があり、葉脈は木質化して伸び2~5対の棘となりますが、老木では先端を除いて全縁のものが多く見られるようになります。ヒイラギの名は、葉の鋸歯が鋭く尖り、触ると痛む(疼ぐ)ことから「疼・柊(ひいら)木」と呼ばれています。この棘のあるヒイラギの葉は邪気を追い払うとし、節分の夜に魔よけとして門にさす風習もあります。 |


 イギリスの貿易商サムエル・コッキングが収集したとされ、江の島サムエル・コッキング苑で見ることができます。
イギリスの貿易商サムエル・コッキングが収集したとされ、江の島サムエル・コッキング苑で見ることができます。