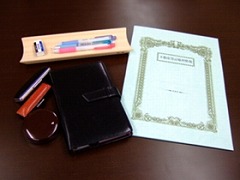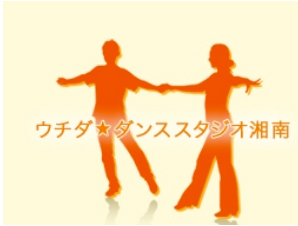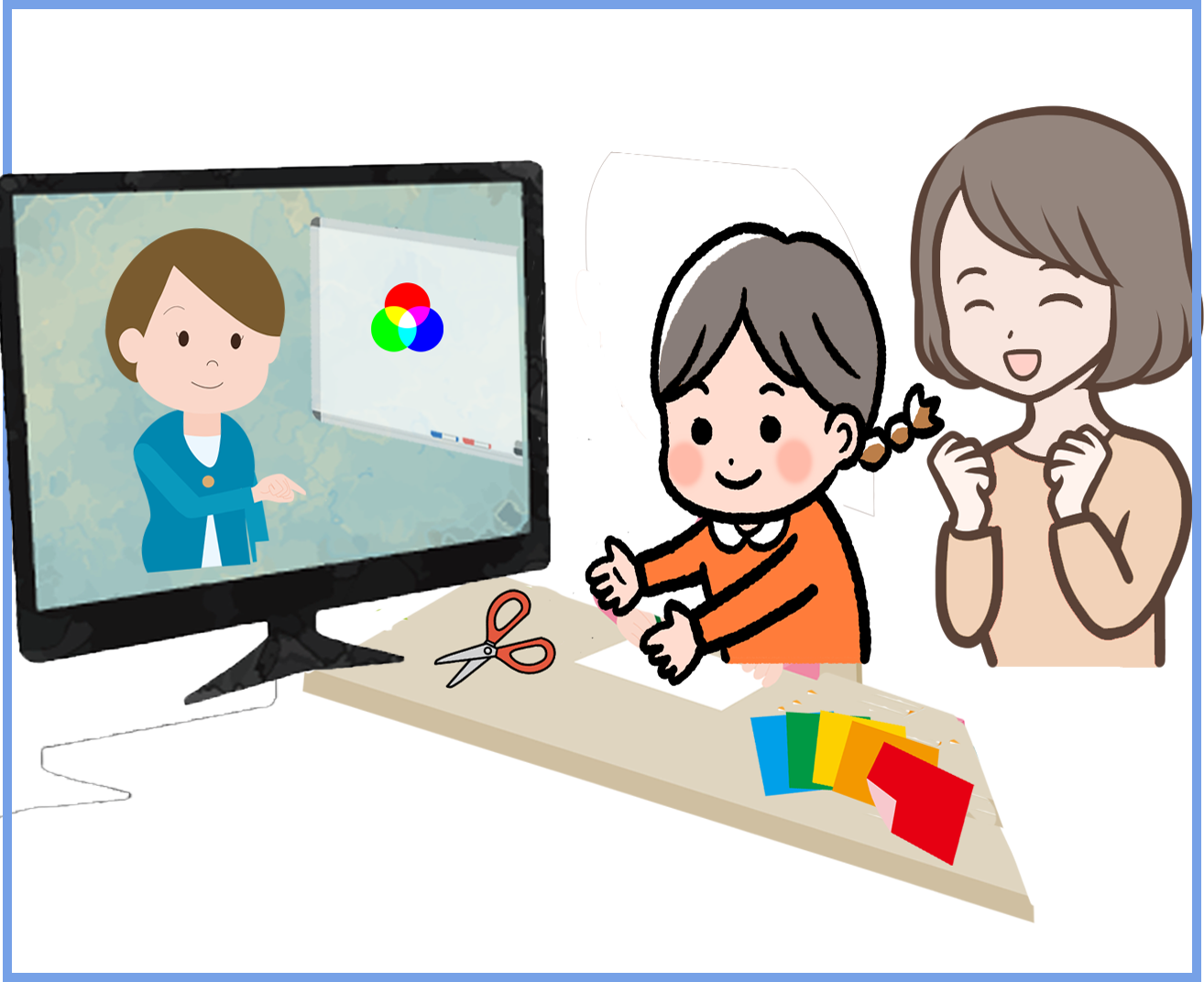江の島の植物・カキドウシ
2022年03月10日 写真&文:坪倉 兌雄
 江の島に咲くカキドウシの花
江の島に咲くカキドウシの花カキドウシ(垣通し)Glechoma hederacea var. grandisは、シソ科カキドオシ属の多年草で、北海道、本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い道ばたや草むらに生え、江の島では参道わきや空き地、広場の片隅などで見ることができます。茎は四角柱状で直立し、高さは5~25㌢になりますが、花が終わるころには倒れて、節から根をだしながら地表をはい、つる状になってふえます。葉は対生し、葉柄の長さは3~4㌢で白毛が密生します。葉は腎円形で基部は心形、長さは1.5~3.5㌢、幅2~5㌢でふちに鈍い鋸歯があります。花期は4~5月、葉腋に淡紫色の唇形花を1~3個ずつつけます。花冠は2唇形で、長さは1.5~2.5㌢、上唇の先はやや凹み、下唇は中裂し、中央裂片は大きく前に突き出て、淡紫色の斑点があり、基部に白毛があります。
 葉は腎円形でふちに鈍い鋸歯がある
葉は腎円形でふちに鈍い鋸歯がある 葉腋に淡紫色の唇形花をつける
葉腋に淡紫色の唇形花をつける 花の内側に淡紫色の斑点がある
花の内側に淡紫色の斑点がある 葉柄に下向きの白毛が
葉柄に下向きの白毛が 龍野ヶ丘広場にて
龍野ヶ丘広場にて萼は5裂して、裂片の先は尖ります。雄しべは4個あり、雌しべの柱頭は2裂します。種子は分果で楕円形。和名の由来は、つるが地を這い垣根を通り越して、さらにのびることからカキドウシ(垣通し)に。別名でカントリソウまたはレンセンソウ(連銭草)などと呼ばれ、古くから子供の癇(かん)をとる民間薬として用いられたことによります。全草に各種の薬効成分があり、茎葉を揉むとほのかによい香りがします。全草に精油(プレゴン、α-、β-ピネン、ピノカンフォン、メントンなど)を含み、生薬名では連銭草(れんせんそう)とよび、糖尿病、腎臓病、湿疹、小児の癇や虚弱体質に用いられ、また生の葉の汁は水虫やたむし、などにも効果があるとされています。参考文献:薬になる植物図鑑。
記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2022年03月10日
2022年03月10日


 江の島では参道わきや空き地、広場の片隅などで見ることができます
江の島では参道わきや空き地、広場の片隅などで見ることができます