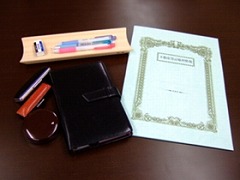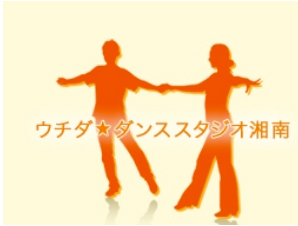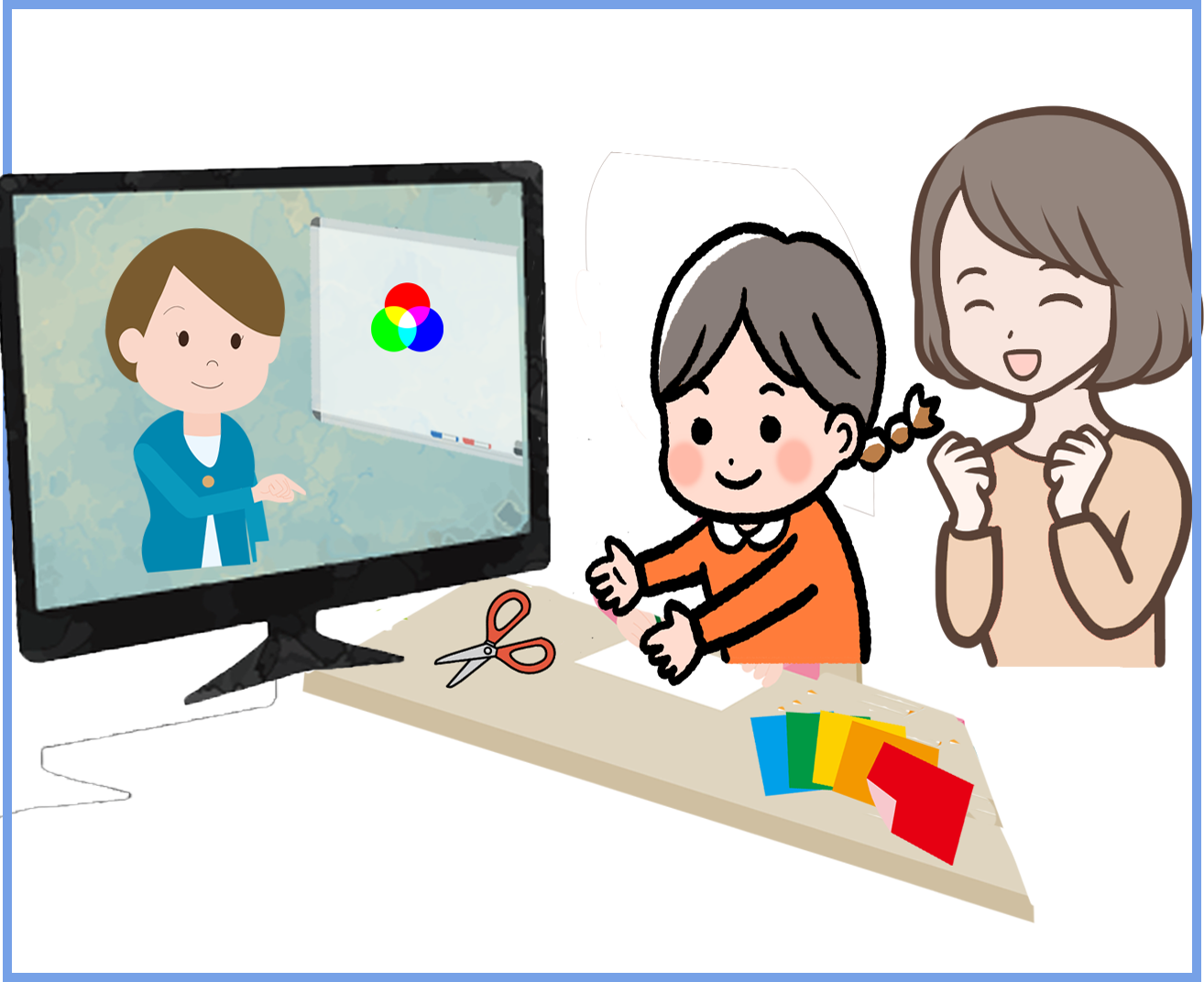江の島の植物・シマトネリコ
2023年8月10日 (坪倉兌雄)

シマトネリコ(島十練子)Fraxnus griffithiiはモクセイ科トネリコ属の半落葉高木で、雌雄異株、亜熱帯や熱帯の山地に自生し、樹高10~18㍍になります。江の島では、住宅の庭先や亀ヶ岡広場などでも見ることができます。株立ちや単幹があり、樹高はおよそ5㍍に、樹皮は灰褐色で、皮目が見られますが比較的滑らかです。葉は対生し、葉柄の長さ3~8㌢、基部は茎を抱き膨らみます。葉身の長さは10~25㌢で、先端の一小葉と、左右に対生する2~6対の小葉からなる、大形の奇数羽状複葉になります。小葉の長さは3~10㌢、幅2~4㌢の長楕円形で全縁、表面に光沢があり、葉縁は波打ち、裏面は淡緑色で葉先は尖ります。花期は5~6月、本年枝の先や葉腋から円錐花序をだし、白い小さい花を多数つけ、花冠の先端は4裂して反りかえります。





果実は翼果で白色、長さ2~3㌢の細長いへら形の倒披針形で、多数つき樹冠を白く飾ります。翼果の中には細長い赤褐色の種子があり、風によって飛散します。本州の中部以北に分布するトネリコは、シマトネリコによく似ています。両者の大きな違いは、前者は落葉樹で、後者のシマトネリコは常緑樹(半常緑樹)です。いずれも樹皮には薬効成分があり、生薬として解熱・鎮痛・眼疾に効果があるとされています。樹木は公園樹や、庭木などによく用いられ、材は緻密で弾性があり、曲木細工に適し楽器などの器具材に使用され、家具や農機具、野球バットなどにも使われています。和名の由来は、トネリコの仲間で、沖縄諸島に自生することから、シマ(島)を付して、シマトネリコ(島戸練子)になったとされています。トネリコの名の由来は、一説には、古来、写経の際に、この木の皮を煮てニカワ状にし、これに墨を混ぜて練ったものを使ったことから、トモネリコ(共練濃)が転訛したもの。また一説には、トヌリノキ(戸塗の木)」の転訛で、この樹皮につくイボタロウ虫が分泌する水蠟樹蠟(いぼたろう)を、戸辷りなどに用いたことによる。この二説があります(参考資料:語源辞典)
記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。 2023年08月10日